筑波宇宙センターの建造物

等価コイル室(磁気試験設備の1つ)
JAXAの造形
筑波宇宙センターの建造物
「初めて筑波宇宙センターに赴任したときには、施設の外見からどんな機能を持っているのだろうと、とてもワクワクしました」と語るのは、施設部の多田麻也子。
筑波宇宙センターにある建造物は、宇宙に関わる特殊なミッションを担って建てられたため、一般的な建造物とは確かに見た目が違う。その造形の面白さについて、同じく施設部の田渕豪はこう語る。「高さ14メートルものシャッターがある施設は、筑波宇宙センターならではだと思います。1990年代から2000年代にかけて、人工衛星が大きくなっていくのに合わせて、シャッター含め施設のサイズも大きくなっていきました。ただ、最近の宇宙業界のトレンドとしては人工衛星も小型化し、多数の衛星を連携させる衛星コンステレーションが主流に。大きくなった施設をこれからどう使っていくのか。実は、その岐路にあると思っています」。
このように、建造物の造形から、宇宙開発の流れも紐解けるという。機能の表出たる造形に、焦点を当てた。
飛ぶ!?と言われた、給水塔
筑波宇宙センター開設時からあった給水塔(高架水槽)は、現在でもセンター内に水を供給している。まだ周囲に建造物の少なかった時代にはランドマークとしても認知されていた。当時は「この上の部分が飛んでいくのか!?」と地元の人から言われたこともあるとか。JAXAのロゴの上にあるのは、(JAXAの前身のひとつである)「NASDA」のロゴ。一度は塗装して消したが、はがれて露出している。


先端テクノロジーを詰め込んだ、
総合開発推進棟
IT化や地球環境配慮などをテーマとした総合開発推進棟(総開棟)は、本部機能を併せ持つ研究施設だ。2003年竣工ながら、現在でも通用する先端的なテクノロジーで構成されている。反射光によって室内空間にも光を届ける光ダクト、1階の床下に免震層を設けて施設と地盤を絶縁する、当時としては先端技術であった基礎免震構造などを採用。全長50mのH-IIロケットと共に、筑波宇宙センターのシンボル的な存在となっている。ロケットを垂直に立てると、総開棟の高さとほぼ同じに。

拡張と増床を想定していた、
広報・情報棟
筑波宇宙センターで最初に建てられた施設のひとつが、旧管理棟(現広報・情報棟)。当時はすべての職員がここで働いていた。現在は見学ツアーの受付などがあり、一般の方でも入ることができる(一部)。多くの建材を事前に工場で製造するプレキャスト工法によって建てられ、あらかじめ拡張することが想定されていた。横方向には3回延伸されている。また階を積み上げることを想定し、階段のための空間が確保されており、屋上には柱を乗せるための四角い突起がある。(結局、階上に拡張されることはなかった)
鉄などの磁性体を使わずに建てられた、磁気試験棟
鉄など磁気を帯びる金属(磁性体)を一切使わずに建てられた無筋コンクリート造。まるで前方後円墳のような、独特の造形となっている。上部のドーム部分は、アルミフレームに木質パネルを貼り合わせて作られているため、非常に軽量。わずかな磁気でも試験に影響するため、半径300m以内に他の建造物は作れないことから、周囲に以前からの雑木林を残している。また施設に接続されているパイプラインは、空調を送るためのもの。


宇宙飛行士を目指すなら、宇宙飛行士養成棟
その名の通り、宇宙飛行士養成棟には、宇宙飛行士を養成するための特殊な設 備がある。モジュール内に居住空間を作り、閉鎖環境を模擬する「閉鎖環境適応訓練設備」のほか、宇宙飛行中の空気漏れや気圧低下など、緊急時の対処を学ぶ「低圧環境適応訓練設備」、宇宙飛行士の訓練時の健康管理を行うための設備など。入り口には、実寸大の宇宙服(レプリカ)や、JAXA歴代の宇宙飛行士の写真が掲げられている。



無機的な存在感を放つ、
標識のデザイン
広大な筑波宇宙センター内に点在する、幾何学的な標識のデザイン。「宇宙実験棟」「宇宙ステーション試験棟」など、宇宙機関ならではの名称が並んでいる。入り口付近に元となるサインがあり、そのデザインに合わせて統一しているという。

人工衛星のサイズに合わせた、
総合環境試験棟
シャッターの高さは約14m。これは、大型の人工衛星を入れるための特注品だ。このシャッターの奥には「衛星通路」と呼ばれる所があり、さまざまな試験設備につながっている。
Profile
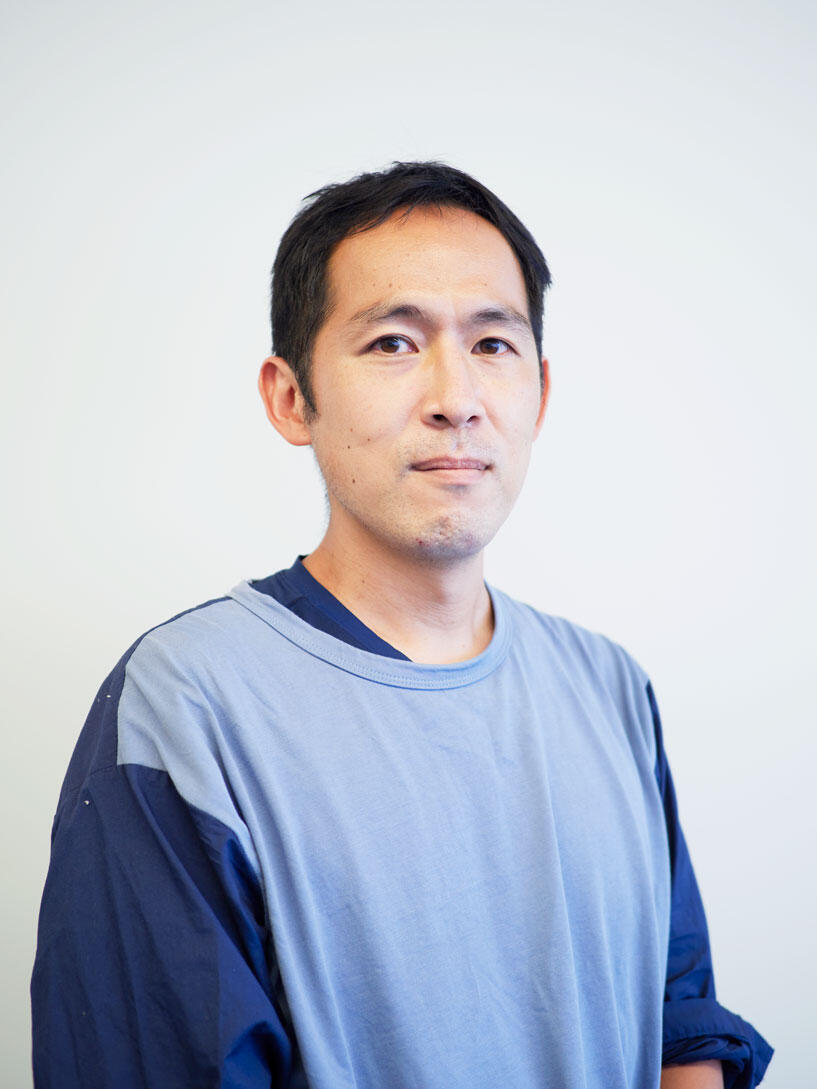
施設部 施設第1課 課長
田渕豪
TABUCHI Go
東京都出身。試験設備の保安距離ならびに耐爆構造物の検討、衛星試験棟等の施設の整備担当を経て、東日本大震災後の復旧作業に従事。その後、人工衛星の事業計画の策定、GREATプロジェクトを担当し現職。趣味は、子どもの幼稚園の送り迎え。そろそろ小学生になるので、次の目標を捜索中。

施設部 施設推進課 研究開発員
多田麻也子
TADA Mayako
東京都出身。JAXA内の建築物の整備、新築・改修設計の発注・監理、施設・構造物情報を集約するDX化を行う。趣味はスノードーム集め。最近ウクレレを始めた。
写真:森本美絵 取材・文:村岡俊也
著作権表記のない画像は全て©JAXAです。


